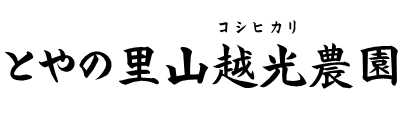お米の特徴
①稲の生育環境
市場では、コシヒカリの最高峰は「南魚沼産コシヒカリ」として認知されていますが、その中でも特別視されている地域があります。
南魚沼盆地の魚沼丘陵西山地域です。南魚沼産コシヒカリの栽培標高は概ね200mの地で行われていますが、この西山地域に位置する吉里地区は地区の後ろに控える西山からの扇状地形で標高250mの田んぼです。山からの豊富な養分で育ったお米は各段の食味であるとの評判です。
更に、私達は、その西山の中腹標高350mに田んぼがあります。
山間地域に位置する圃場は、稲の生育にとって過酷な条件です。
南魚沼盆地の夏の蒸し暑い気候と昼と夜の寒暖差の激しいことが稲にとっては過酷そのもの、その環境で付ける穂は70%に満たないのです。
しかし、この環境に耐えて付けた穂に田んぼの恵みが全て凝縮されています。
食べた食感として、もちもち感と本来の甘みが群を抜いています。この食味はこの地域の田んぼからでしか得られないと自負しております。
また、圃場は全く人家はありません。生活排水混入の心配がまったく無いのです。周りの環境に左右されない天水のみで稲は育ちます。

②特別な肥料
お米の付加価値を議論する際、ひとつの指標が有機肥料か化学肥料かがあります。
化学肥料はテクノロジーで即効性のある肥料として開発され、稲の生育が安定し結果として面積当たりの収量が上がるとして、一般的に広く使用される様になっています。一方、市場でのお米の高付加価値化に目を向けると、差別化の指標として有機肥料栽培が導入され、市場価値を左右するようになりました。
子ども達が美味しいと言ってお代わりしてくれるシチュエーションを夢見て取り組んでいる私達のたどり着いた答えは、テクノロジーの活用です。
化学肥料の良いところを有機肥料に加えた混合肥料栽培を行なっています。
一例を挙げると、植物の生育に欠かせない3代栄養素は窒素・リン酸・加里ですが、肥料の中に存在する水溶性リン酸は通常15%程度であり、稲は最大15%までしか吸収できません。
しかし、化学の力を借りて水溶性リン酸分を80%まで高める特別なボカシ肥料を加えることで食味の格段の向上に役立っているのです。
③極低農薬
半世紀前の農薬技術は害虫駆除・除草を担保する為に、毒性が強いものでした。
実際に使用した結果、田植えの田んぼで”どじょう”や”おたまじゃくし”などが大量に白いお腹をみせて漂っていたことが鮮明に思い出されます。
その後改良が重ねられ環境にやさしい農薬が流通する様になっていますが、本当に”人にやさしい”をとことん考え農薬使用限界に挑戦しています。
今は、圃場内の農薬散布は通常田植時1回だけ(一般栽培米比8割減)で行っています。
加えて、広大な畦畔・道路水路はいっさい除草剤は使用していません。全て年間を通じて全面草刈りで対応しています。




④雪中熟成
お米は呼吸しています。収穫後鮮度を保つ条件を知り、お米の鮮度を保つ工夫をしています。
鮮度を保つ条件はいったい何でしょう?
答えはこの地方に古くから伝わる保存方法にありました。
収穫した籾を山に設けた人工の洞窟に入れ冬の間3mの雪が覆っていました。 これが”雪室”です。
雪室を紐解くと、自然の力で適度な温度と湿度環境でお米は眠りについていたのです。
この条件を知った上で、先人の知恵を現代のテクノロジーで近づける探求に取組んでいます。
雪室を再現した専用冷蔵庫を導入し、雪の季節は3mの雪ですっぽり覆われた倉庫に閉じ込める環境を作りました。
雪に覆われた天然の冷蔵庫内は5℃以下の状態を保ち、ここで寝かせることでお米は熟成されるのです。
⑤鮮度保持お届け
お米の劣化を最小限に抑える為に、お届け直前に精米することに加え、精米後直ぐに真空包装(30kg袋は除く)してお届けします。
未開封であれば、冷蔵庫で約2年間(目安)は鮮度が保持できるため、災害時の備蓄用としても便利です。